栃木県北部を中心に活動している健康運動指導士の佐藤崇子です。
地域の皆さんが毎日を笑顔でよりよく生きるため日常生活動作に着目し、
いくつになっても楽で快適に動ける身体づくりをお伝えしています。
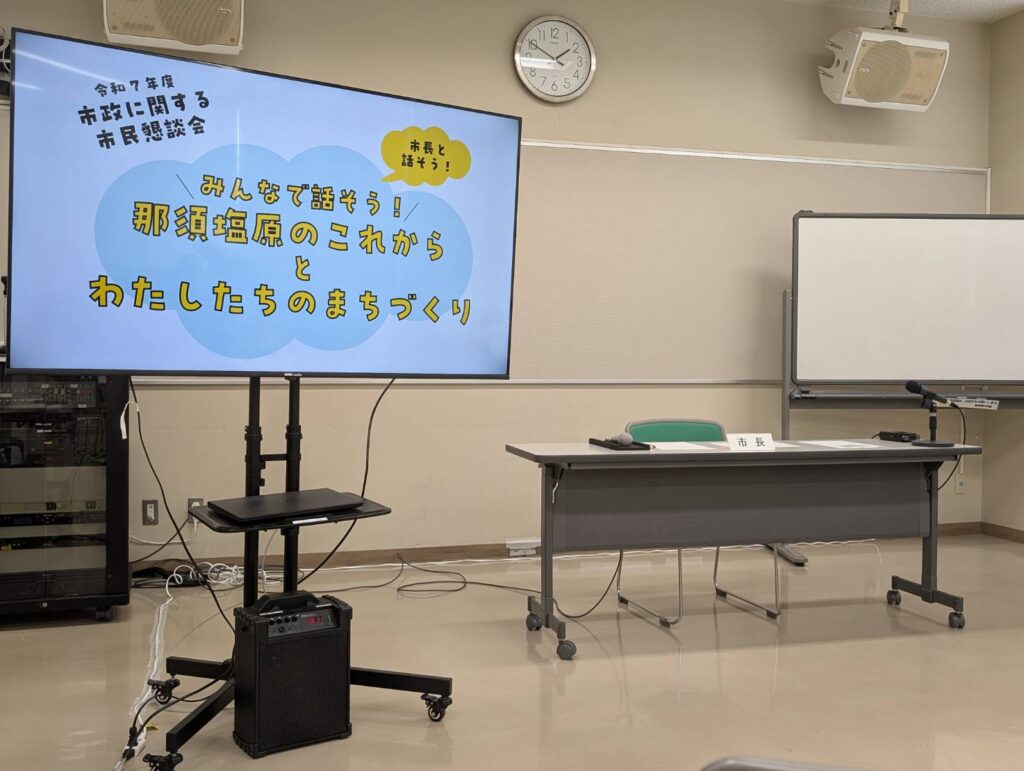
8月末、サークルでもお世話になっている公民館館長から
「運動の大切さを伝える良い機会では?」と
【令和7年度市政に関する市民懇談会】への参加を提案されました。
開催前日の連絡でしたが、思い切って参加することにしました。
この懇談会は市長が直接市民の声を聴くという貴重な会です。
初めての雰囲気にドキドキしましたが、
以前から温めていたプレゼン資料も持参して臨みました。
子どもたちの現状から見えてきたこと
私は日本コアコンディショニング協会(JCCA)認定講師も務めています。
セミナーでは体幹の重要性とエクササイズをお伝えしており、
その中で赤ちゃんの発育発達過程とともに、
今の子どもたちの現状についても触れています。
すると受講生の方々から驚くようなお話を伺いました。
・ある小学校の先生からのお話では、
「授業中に3分の1の児童が椅子から滑り落ちて机からいなくなってしまう」とのこと。
給食時も座っていられず時間内に食べ終えることも一苦労だそうです。
・ある治療家さんからは、
「小学校で跳び箱を跳んだら両手首を骨折した子がいて、その小学校では跳び箱が中止になった」
というお話も伺いました。
捻挫かと思ったら骨折していた、というケースも増えているそうです。
・あるママさん運動指導者のお子さんは、
「6Bの鉛筆」を使っているそうです。
私が小学生だったころはHBの鉛筆が主流でしたが、
今は筆圧が弱い子が増え、学校から2Bの鉛筆が指定されることも珍しくないようです。
・全国の講師からは、
雑巾がけで突き指をした子が出たため、安全配慮から雑巾がけが掃除から除外された小学校の話も聞きました。
こうした話は、私が子どもの頃にはなかったことです。
テレビのニュース番組でも「子どもロコモ」として、
子どもたちの体に異変が起きていることが特集されていました。
・5秒以上ふらつかずに片足立ちをすることができない
・しゃがみ込む時に途中で止まったり、後ろに転んでしまう
・両手を上げた時、手の先から肩にかけて垂直にならない
・前屈の際に膝を伸ばしたまま手の指を床につけることができない
上記の4項目のうち1つでも該当する場合、「子どもロコモ」が疑われるそうですが、
このような子どもが増えているというのです。
私の住む市の小学校では授業開始時に「立腰」と声をかけるそうです。
骨盤を立てて良い姿勢で授業に臨むという意図ですが、
その姿勢を維持するために必要なのが【体幹】です。
身体のコアを育む機会が失われている
人間は生まれてから立って歩けるようになるまでの各過程で、
体幹(コア)の機能を獲得していきます。
しかし、住居環境(スペース)の変化、コロナ禍での活動制限、
治安や公園遊具の撤去などによる外遊びの減少、
そしてスマホやゲームの普及によって、
体を動かす機会が減ってしまいました。
その結果、コアを鍛える機会や経験が少ないまま成長しているのです。
これが椅子に座っていられない、手をついたら骨折する、筆圧が弱い、
雑巾がけをうまく制御できない、子どもロコモといった
子どもたちが増えている原因かも知れません。
【学校体育にコアコンを!】
そこで私は、「学校体育にコアコンディショニングを導入してほしい!!」
という夢を持つようになりました。
遊びの中でできる【コアキッズ体操】を体験してほしいのです。
この体操は日本コアコンディショニング協会のコンテンツで、
9つの体操を順番に行うことで
発育発達過程を再学習し、その子が本来もっている能力を引き出すことができます。
運動が苦手な子どもたちでも、「いつの間にかできた!」という成功体験につながるはずです。
そして、椅子に座って授業に集中できる、文字もしっかり書ける、
しゃがむ・万歳・前屈といった動きもスムースにできる子が増えると思うのです。
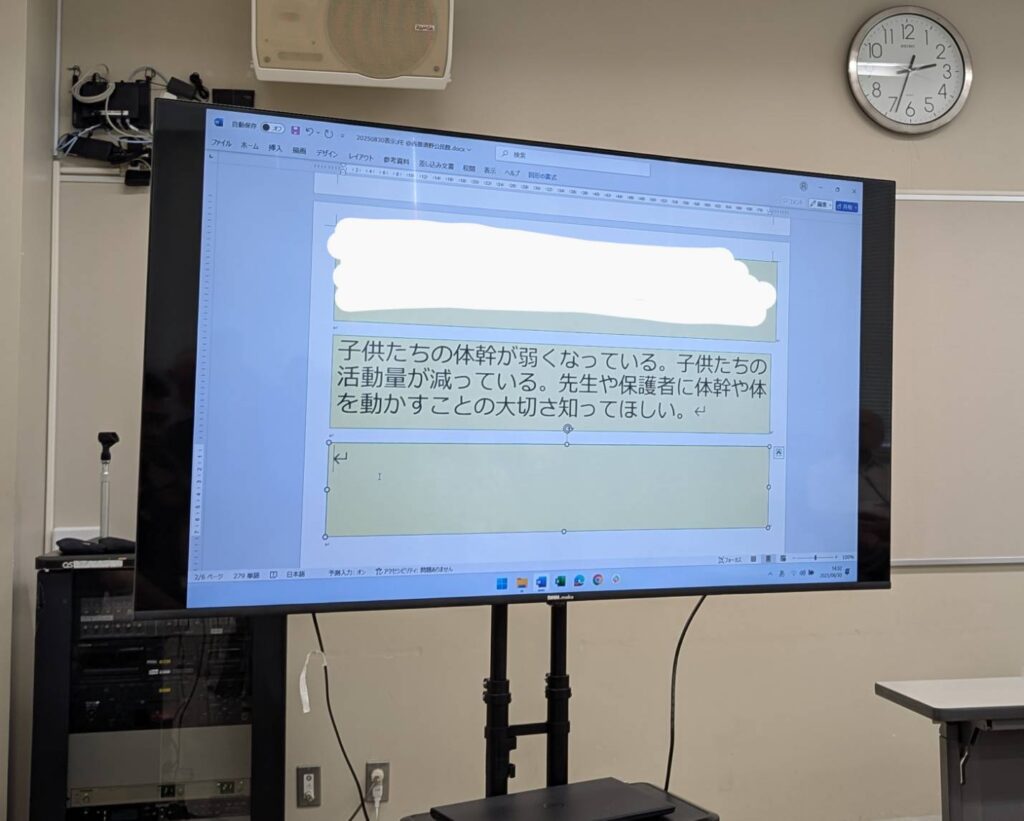
夢の第一歩
懇談会では、これらの内容を学校の先生や保護者の方にも知ってほしいとお話させていただき、
プレゼン資料も無事受け取っていただけました。
話を聞いた司会の方からは「スポーツテストの結果が年々悪くなっている」というお話や
市長からも体幹の必要性について理解のある言葉をいただきました。
「学校体育にコアコンを!」という考えを学校の先生や校長先生に聞いてもらうことが
今年の目標の一つでした。
それがなんと直接市長にお伝えできたこの日は、
私にとって貴重な一日となりました。
とはいえ、これで何かが始まったわけではありません。
これからも地道に発信していきたいと思います。








